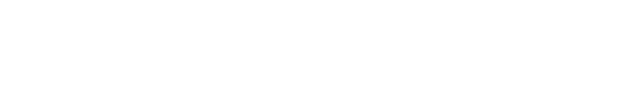マインドフルネスとは?実践方法を解説
目まぐるしく変化する現代社会。仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、SNSからの情報過多…私たちの心は常に様々な刺激に晒され、知らず知らずのうちに疲弊しているかもしれません。「なんだか落ち着かない」「頭の中がごちゃごちゃする」「ストレスを感じやすい」と感じているなら、それはあなたの心がSOSを発しているサインかもしれません。
そんな現代を生きる私たちに、いま注目を集めているのが「マインドフルネス」です。今回は、マインドフルネスが一体どんなものなのか、そしてその効果や実践方法、マインドフルネスの科学的エビデンスについて、詳しくご紹介していきます。
マインドフルネスとは?
マインドフルネスとは、「今この瞬間の体験に、意識して、評価を加えることなく、注意を向けること」と定義されます。簡単に言えば、「今、この瞬間に何が起きているのか」に、ただただ意識を集中する心の状態、そしてその状態を養うためのトレーニングのことです。
私たちは普段、無意識のうちに過去の後悔や未来への不安にとらわれがちです。また、目の前のことに集中しているつもりでも、実は別のことを考えていたり、自動操縦のように行動していたりすることも少なくありません。例えば、食事中にスマホをいじって味をよく覚えていなかったり、通勤中に景色を見ずに考え事をしていたりといった経験は誰にでもあるでしょう。
マインドフルネスは、こうした「心のさまよい」から抜け出し、「今、ここ」に意識を戻す練習です。呼吸、体の感覚、聞こえてくる音、目に見えるもの、感情、思考など、五感を通して得られるあらゆる情報に、良い悪いの判断を下さずに、ただありのままに注意を向けます。
これは、現実から目を背けることでも、ポジティブ思考を無理強いすることでもありません。むしろ、喜びも悲しみも、快適さも不快さも、ありのままの自分と向き合うことです。それによって、私たちは自分の感情や思考のパターンに気づき、それらに振り回されることなく、より建設的に対処できるようになるのです。
マインドフルネスを実践してみよう
「マインドフルネス」と聞くと、なんだか難しそう、特別な人がやるもの、といったイメージを持つ方もいらっしゃるかもしれません。しかし、実はとてもシンプルで、日常生活の中で誰でも実践できるものです。
では、実際に簡単なマインドフルネス瞑想を体験してみましょう。
- 姿勢を整える: まずは椅子に座るか、床にあぐらをかいて座ります。背筋を軽く伸ばし、肩の力を抜いてリラックスしましょう。手は膝の上や太ももの上に置き、手のひらは上でも下でも構いません。
- 目を閉じる、または半目にする: 完全に目を閉じても良いですし、視線を斜め下に向けて半目にしても構いません。
- 呼吸に意識を向ける: ゆっくりと鼻から息を吸い込み、口から息を吐き出します。このとき、お腹が膨らんだりへこんだりする感覚や、空気が出入りする感覚に注意を向けましょう。呼吸の深さや速さは意識的に変えず、自然な呼吸を観察します。
- 雑念が浮かんでもOK: 呼吸に意識を向けていると、きっと様々な考えや感情が頭に浮かんできます。「今日の晩ご飯は何にしようかな」「あの仕事、まだ終わってないな」など、どんな雑念が浮かんでも大丈夫です。それを無理に追い払おうとせず、「あ、考えているな」と気づいたら、そっと意識を再び呼吸に戻します。
- 音や感覚に気づく: 呼吸に慣れてきたら、部屋の音や体の感覚(服が肌に触れる感じ、床に接している部分の感覚など)にも意識を広げてみましょう。それらを「良い」「悪い」と判断することなく、ただ観察します。
この短い瞑想を数分間行うだけでも、頭の中が少しスッキリしたり、心が落ち着いたりする感覚を味わえるかもしれません。これが、マインドフルネスの第一歩です。
マインドフルネスの科学的エビデンスはあるの?
「マインドフルネス」という言葉だけ聞くと、スピリチュアルなものや、単なるリラクゼーション法のように感じる方もいるかもしれません。しかし、近年、マインドフルネスは科学的なアプローチによってその効果が数多く研究され、多くのエビデンスが蓄積しつつあります。
特に、神経科学の分野では、マインドフルネス瞑想が脳に与える影響が詳細に分析されています。研究によって、以下のような変化が報告されています。
- 脳の構造の変化: マインドフルネス瞑想の継続的な実践により、感情の制御や自己認識に関わる前頭前野や、記憶や学習に関わる海馬の灰白質が増加することが示されています。一方で、ストレス反応に関わる扁桃体の灰白質が減少するといった報告もあります。これは、ストレスへの反応性が低下し、感情のコントロールが向上することを示唆しています。例えば、Hölzel et al. (2011) の研究では、8週間のマインドフルネス瞑想プログラム(MBSR)に参加した人々の脳構造に変化が見られたことが報告されています。
- 脳機能の変化: 瞑想中に、デフォルトモードネットワーク(DMN)と呼ばれる、心がさまよっているときに活性化する脳の領域の活動が抑制されることが示唆されています。
- ストレス軽減: ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌抑制や、心拍数や血圧の低下など、ストレス反応が緩和される可能性が報告されています。
- メンタルヘルス疾患への効果: うつ病の再発予防、不安障害、パニック障害、強迫性障害の症状軽減に有効である可能性が複数の研究で示唆されています。特に、マインドフルネス認知療法(MBCT)は、うつ病の再発予防効果のエビデンスが蓄積し、英国国立医療技術評価機構(NICE)のうつ病治療ガイドラインでも寛解後の再発予防治療として言及されています。
- 集中力と注意力の向上: マインドフルネスの実践により、目の前のタスクに集中しやすくなり、生産性の向上などが期待できる可能性があります。
- 睡眠の質の改善: 不眠に悩む人々の睡眠の質向上との関連について報告されています。
- 痛みの緩和: 慢性的な痛みを抱える人々に対して、痛みの感覚そのものを変えるのではなく、痛みに対する心の反応を変えることで、痛みの苦痛を軽減する可能性について示唆する報告があります。
このように、マインドフルネスは単なるリラクゼーションを超え、私たちの心身に具体的な良い影響を与える可能性が、科学的研究によって示されつつあります。
[1]: Hölzel, B. K., Carmody, S. J., Vangel, M., Congleton, A., Yerramsetti, S. B., Gard, T., & Lazar, S. W. (2011). Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter density. Psychiatry Research: Neuroimaging, 191(1), 36-43.
[2]: Kuyken W, Warren FC, Taylor RS, Whalley B, Crane C, Bondolfi G, Hayes R, Huijbers M, Ma H, Schweizer S, Segal Z, Speckens A, Teasdale JD, Van Heeringen K, Williams M, Byford S, Byng R, Dalgleish T. Efficacy of Mindfulness-Based Cognitive Therapy in Prevention of Depressive Relapse: An Individual Patient Data Meta-analysis From Randomized Trials. JAMA Psychiatry. 2016 Jun 1;73(6):565-74.
[3]: National Institute for Health and Care Excellence (NICE). (2022). Depression in adults: recognition and management. NICE guideline [NG222].
まとめ:今日から始めるマインドフルネス
マインドフルネスは、忙しい現代を生きる私たちにとって、心の健康を保つための強力なツールとなり得ます。特別な道具も場所も必要なく、いつでもどこでも実践できる手軽さが魅力です。そして、その効果は科学的にもエビデンスが示されつつあります。
「今、ここ」に意識を向けることで、私たちはストレスに強くなり、感情をよりよく理解し、集中力を高め、そして何よりも、より豊かな人生を送るための心の安定を手に入れることができます。
まずは、今回ご紹介した簡単な瞑想から、あるいは興味を持ったアプリやWebページを試してみることから始めてみませんか? きっと、あなたの日常に穏やかでポジティブな変化が訪れるはずです。今日から、マインドフルな一日を始めてみましょう。
記事監修者について
こころの港クリニック京橋・東京駅前 院長
医学博士
日本専門医機構認定精神科専門医
日本精神神経学会精神科専門医制度指導医
精神保健指定医