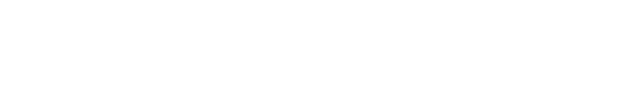月経前症候群(PMS)/月経前不快気分障害(PMDD)
月経前症候群(PMS)/月経前不快気分障害(PMDD)はどんな病気ですか?
月経前症候群(PMS)は、月経の約3〜10日前頃に現れる身体的・精神的な不調を特徴とする症状群で、月経が始まるとともに症状がおさまったり、なくなったりすることが特徴です。
PMSかどうかを見極める上で重要な点は、下記のとおりです。
- 月経の前にだけ不調が現れている
- 同じような症状が毎月繰り返されている
- 日常生活に影響が出ている
- 症状が3カ月以上続いている
月経前不快気分障害(PMDD)は、「イライラする」「気分が落ち込む」「不安」「怒りっぽくなる」といったPMSよりも重い精神的な症状を伴い、日常生活や社会活動に支障をきたす場合に診断される可能性があります。
PMSは月経のある女性の50~80%に見られる一般的な症状ですが、PMDDは約2~6%の方に該当するとされています。
「月経に伴う避けられない症状だ」と考えている方も多いですが、実は適切な治療を受けることで症状を大きく緩和することが期待できます。
月経前症候群(PMS)/月経前不快気分障害(PMDD)でよくみられる症状は?
PMSとPMDDでは症状の種類は似ていますが、PMDDでは特に精神的症状が顕著で、重症化しやすいのが特徴です。
以下は代表的な症状です。
からだの症状
- 腹痛や腰痛、頭痛
- 乳房の張りや痛み
- むくみ、体重増加
- 疲労感
こころの症状
- イライラや怒りっぽさ
- 気持ちの落ち込み、無気力
- 不安感や緊張感
- 集中力の低下
行動面の変化
- 食欲の変化(過食や甘いものを欲する)
- 睡眠障害(不眠または過眠)
- 社会的な引きこもり
PMDDではこれらの症状が極めて強く、仕事や人間関係などに深刻な影響を与えることが特徴です。
月経開始後は症状が急速に軽減または消失することが多いです。
月経前症候群(PMS)/月経前不快気分障害(PMDD)の治療にはどんな選択肢がありますか?
生活習慣の改善
- 症状日記をつけることで、症状が出現するタイミングやパターンを把握でき、対処がしやすくなります。最初に取り組むことをおすすめします。
- バランスの良い食事(ビタミンB6やカルシウム、マグネシウムを積極的に摂取)や定期的な運動、十分な睡眠は、PMSやPMDDの症状を和らげるのに役立ちます。
- アルコールやカフェインの摂取を控えることで、緊張感やイライラを軽減できる場合があります。
薬物療法
ピル(経口避妊薬:低用量ピルなど)
月経前症候群は、排卵後に分泌される黄体ホルモンが影響していると考えられています。
経口避妊薬(ピル)によって排卵を抑えることで、このホルモンの分泌が減り、結果として症状の軽減が期待できます。
ピルは基本的に安全性の高い薬剤ですが、まれに血栓症などの副作用が生じる可能性があります。安全な処方のため、ほとんどの場合、婦人科の専門の医療機関で処方されています。
漢方薬
比較的副作用が少ないことから、PMS(PMDD)の治療ではよく用いられます。
体質や症状に合わせて処方されます。
- 漢方薬の種類
-
加味逍遥散:気の巡りと熱を整え、イライラやのぼせがある方向け。
-
当帰芍薬散:冷えやむくみ、痛みに効果があり、体力が低下して疲れやすい方に向く。
-
桂枝茯苓丸:血行を促して熱のバランスを整え、のぼせがある一方で足の冷えがある場合など。
-
抑肝散加陳皮半夏:神経過敏や不眠、ストレスによる緊張が続いている方などがよい対象。
-
抗うつ薬(SSRI:選択的セロトニン再取り込み阻害薬)
PMDDの治療の第一選択はSSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)です。不安感や抑うつ症状を軽減する効果が示されています。
PMDDの場合、SSRIは継続して内服する、または黄体期の2週間(※排卵後〜次の月経が始まるまでの期間)服用すると最も効果が出やすいとされていますが、PMDDの症状が強くなる、「月経直前の6日間程度」のあいだ服用するだけでも一定の効果があるとされています。
SSRIの中でも下記の薬剤は、PMDDに対する治療効果が認められています。
| 成分 | 薬剤名 |
|---|---|
| セルトラリン | ジェイゾロフト |
| エスシタロプラム | レクサプロ |
| パロキセチン | パキシル |
比較的低用量でも効果が期待できるので、用量調整がしやすく離脱症状も強くないセルトラリン(ジェイゾロフト)が使われることが多いです。
月経前症候群(PMS)/月経前不快気分障害(PMDD)の治療で気をつけることは?
PMSやPMDDは月経周期と密接に関連しているため、症状の記録を取ること(症状日記)で、治療の効果を測定しやすくなります。
婦人科と精神科・心療内科で別々に治療を受けるケースも少なくないため、2つのクリニックに並行して通院する場合は、治療内容が変わった際の情報共有などは注意が必要です。
文責 山﨑龍一(医学博士、日本専門医機構認定精神科専門医、日本精神神経学会精神科専門医制度指導医、精神保健指定医)