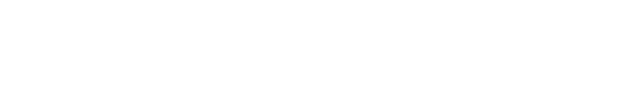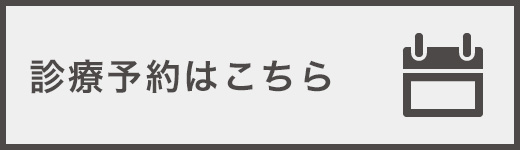睡眠薬の種類と基礎知識
不眠の背後には、生活習慣から心身の病気まで多様な要因が存在します。まずは根本原因の特定とその治療が重要であり、睡眠薬はその補助的役割として活用されます。
不眠を引き起こす主な原因
- 不規則な生活リズムや睡眠習慣
- ストレスや過剰な緊張
- うつ病や不安障害などの精神疾患
- アルコールや薬物の影響
- アレルギーや呼吸器症状など身体的疾患
これらの要因を見極めた上で、まずは睡眠環境や生活リズムの見直し、リラクゼーションの導入など、薬を用いないアプローチから開始するのが基本です。
主な睡眠薬の種類と特徴
1. GABA受動体作動薬
脳内の興奮を鎮める「GABA(ガンマ‐アミノ酪酸、ギャバ)」の作用を強化し、入眠を促進します。代表的な薬は以下の通りです:
- ベンゾジアゼピン系睡眠薬:トリアゾラム(ハルシオン®)、ブロチゾラム(レンドルミン®)、フルニトラゼパム(サイレース®)
- 非ベンゾジアゼピン系睡眠薬:ゾルピデム(マイスリー®)、ゾピクロン(アモバン®)、エスゾピクロン(ルネスタ®)
ベンゾジアゼピン系睡眠薬系は持続時間の調整がしやすい利点がありますが、長期使用により依存や反跳性不眠(薬をやめた反動で眠れなくなること)のリスクが高まる点に注意が必要です。
非ベンゾジアゼピン系睡眠薬は依存性がやや低いとされますが、長期的に使用するとやはり効きづらくなったり、依存が生じることがあります。
2. メラトニン受容体作動薬(例:ラメルテオン/ロゼレム®)
体内時計を整える作用があり、睡眠リズム障害に効果的です。特に若年層や交代勤務など不規則な生活を送る方に向いています。
日中の眠気など副作用に注意し、用量・服用時間の調整をします。通常の用量である8mgで効きすぎる場合もあります。
3. オレキシン受容体拮抗薬(例:スボレキサント/ベルソムラ®、レンボレキサント/デエビゴ®、ダリドレキサント/クービビック®)
比較的新しい睡眠薬で、脳内で覚醒を制御するオレキシン受容体に作用することで自然な眠気を促します。依存や反跳性不眠の心配が少ない一方で、効果の発現まで時間がかかる場合があることや、人によっては夢を見ている時間の増加などの副作用が見られることがあります。
4. 補助的選択肢としての漢方薬
漢方は個々の体質や症状に合わせた処方が可能です。不眠に対しては、「肝」や「心」(西洋医学の肝臓や心臓とは全く異なる概念です)のバランスを整える視点からアプローチします。例えば以下のような処方があります:
- 抑肝散(よくかんさん)
- 酸棗仁湯(さんそうにんとう)
- 加味帰脾湯(かみきひとう)など
漢方薬は効き方が比較的マイルドなことから、睡眠薬の服用に抵抗がある人が希望される場合もあります。
まとめ
睡眠薬はあくまで補助的手段であり、生活習慣や心理的要因へのアプローチが不可欠です。ご自身の不眠のタイプや原因に合った最適な方法を専門医と相談しながら選ぶことが、質の高い睡眠への第一歩です。
文責 山﨑龍一(医学博士、日本専門医機構認定精神科専門医、日本精神神経学会精神科専門医制度指導医、精神保健指定医)